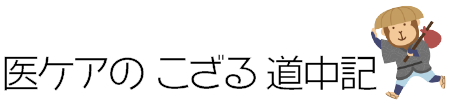必要な支援を認めてもらうには
”親の都合”では認められない
支援学校に通う子供たちは長時間通学は当たり前なんだそうで、スクールバスで2時間かかる子達もいるとか。そんな時間に比べたら”50分が長時間だから無理”というのは理由にならなかったみたいです。
さらに余程の理由でないと認められない、というその”理由”も親の都合の場合は認められないのだそうです。例えば、”送迎をしている母親が仕事をしていて、別の学校の方が近いから”というのはダメなんだそうです。
あくまでも子供にとってどうしても必要な理由でないと、と言われます。親が送迎をしている以上、親の都合は子供にとっても大事だと思うのですが。親が無理をして体を壊しては、子供が通学できないのですから。
この時に連絡をくれた市の担当者の女性はとても感じのいい人で、私がどうしても困るという事を訴えると、子供に関する事で何か余程の理由に当たるものはないかと聞いてくれました。
そこで、
- A校には近くに緊急時に対応している病院が離れているが、C校ならすぐ隣に病院がある上に、かかりつけの大学病院もすぐに行くことが出来るので安心であること。
- 出来れば担当医にすぐ診てもらえる体制の方がこざるにとって安心なこと。
- 以前こざるがインフルエンザにかかり容体が気になって夜間診療で診てもらった時、当直医はインフルエンザだから家で安静にしていれば大丈夫と言われたが、その時たまたま小児外科での担当医がいて”この子は要注意だからと追加の検査をしたら肺炎になっていた”という事があったこと。
- 容態が急変した時に事情を知らない医師が診て手遅れになるかもしれないこと。
などなど最悪の事態になった時に起こり得ることを話して、A校ではなくC校にして欲しいと伝えると、それなら大丈夫だと思います。と言われました。
その時の言葉通り認めてもらえたので、親身に話を聞いてくれた担当者さんに感謝です。
この件で障害関係で行政などに支援などを頼む時は、最悪の事態を想定した話、または状態が良い時でなく悪い時を少し盛ってるかなと思うくらいで伝える方が、認めてもらえることも学習しました。
悪い時を想定して盛ったくらいで話す、ということは決して悪いことではないんですよね。それは、実際に状態が悪い時に必要な支援を受けられるようにするためです。
コーディネーターが欲しい
ここまでたどり着くのに、相談先の学校は”こういう所がありますよ”という紹介を親にするだけで、紹介先と連携が取れているわけではないので、事情や経緯などの説明を毎回親がする必要がありました。
加えて、どんな手続きが必要なのか・就学に関する条件(手帳のこと)などを知る機会がなく、言われるままに動いていたので右往左往です。
拠点となる相談先があったわけでもありません。ある時は幼稚部の先生、ある時はリハビリ施設の先生など、その場だけの相談先で、こざるの就学全般を相談できるわけではありませんでした。
なので、B校に見学に行った時は”聾学校へ行った方がいい”と言われ、C校では手続きとしてA校へ行くように言われ、A校では初めて手帳の件を知らされ、学区外でも認められると簡単に言われたのにとんでもなく苦労したとか、コーディネーターがいたら助かったのに、と思います。
実際に医ケアの子を持つ方ならわかると思いますが、気管切開しているとか胃ろうからの注入が必要だとか、外出先でもケアが必要だと外出そのものが大ごとです。
その為の荷物が多くて準備がまず大変です。さらに出かけるまでにも体調に気を使い、移動の車内でも気を使い、現地に行ってもケアのタイミングや場所に気を使い、こざるの場合はウロウロ動くのでゆっくり落ち着いて話を聞くことも大変です。
予定だからと無理に外出したことでまた疲れを出して体調が崩れることもあります。(親も毎回ぐったりです)
実際に子供を連れて出かける回数は出来るだけ少なくしたいので、電話で済むことなら電話で、できれば自宅に訪問してもらってゆっくり考えたいです。
普通に地域の学校へ行ける子供達と違って、色々制約や手続きがある子たちにはコーディネーターさんが訪問してくれて相談に乗ってもらったり、調整してもらえたら助かるのに、と切に思います。

地元の就学に関する情報に触れる機会がない
“医療的ケア児の就学は大変”という事は、メディアでよく見かけるようになりましたが、自分の地域の実状はどうなのかはさっぱりわかりません。
こざるの地域でも“肢体不自由部のある支援学校には看護師が配置されている”事はわかるのですが、それ以外の知的の支援学校や一般の学校ではどんな状況なのか。
県のホームページを見ても、肢体不自由部への看護師増員の話は載っていても、それ以外はありませんでした。
おそらく個別対応なのだとは思いますが、今は就学の段階で看護師が必要と言ったら、普通に配慮してくれているのでしょうか?
どのくらいの時間、担当してもらえるのでしょうか?
こざるの就学問題は県の管轄内の事だったので、県の対応しかわかりませんが、これが市立の学校だったらどんな対応だったのでしょう?
こざるが通う聾学校には地域の小学校との交流学習があって、付添いで一緒にその小学校へ行った時、下校する子供達の中に医ケアが必要と思われるほぼ水平に倒したバギーに乗った子がいました。
地域の小学校を選択した子なんだな、と思ったのですが、どんな風に学校生活を送っているのか、想像がつきませんでした。実際にうちの自治体で地域の小学校を選択した医ケア児がどのくらいいるのか、知る事は出来ません。
だから、看護師がどのようについているのか(いないのか)ケア専用の場所はあるのか、個別のフォローはされているのか、知る方法もありません。
知り合いでないかぎり、他校の現状は分からないのです。
個人情報保護の関係もあるとは思いますが、就学前の医ケア児を持つ親が地域の小学校を選ぶ時の在学時のイメージは、メディアで見聞きした地元ではない情報が頼りなのではないでしょうか?
地域によって本当に対応が大きく違う事柄なので、いざ就学活動を始めた時に、理不尽に驚く事が沢山出てくるのではないかと思うのです。
希望した学校に既に医ケア児を受け入れた事があれば、教育相談の時に様子を知る事ができるでしょう。でも大抵は初めてだと思います。
公に色々ガイドラインが出来ているとはいえ、実際に受け入れ態勢を作るのは個々の学校です。校長先生他管理職の先生方がどのくらい前向きに考えてくれるかでも大きく違います。

子供の医ケアで24時間気を張り詰めて生活してきた親御さん達の心労が少しでも減るよう、地域の医ケア児就学情報を知る方法があればと思います。
就学問題③へ続く